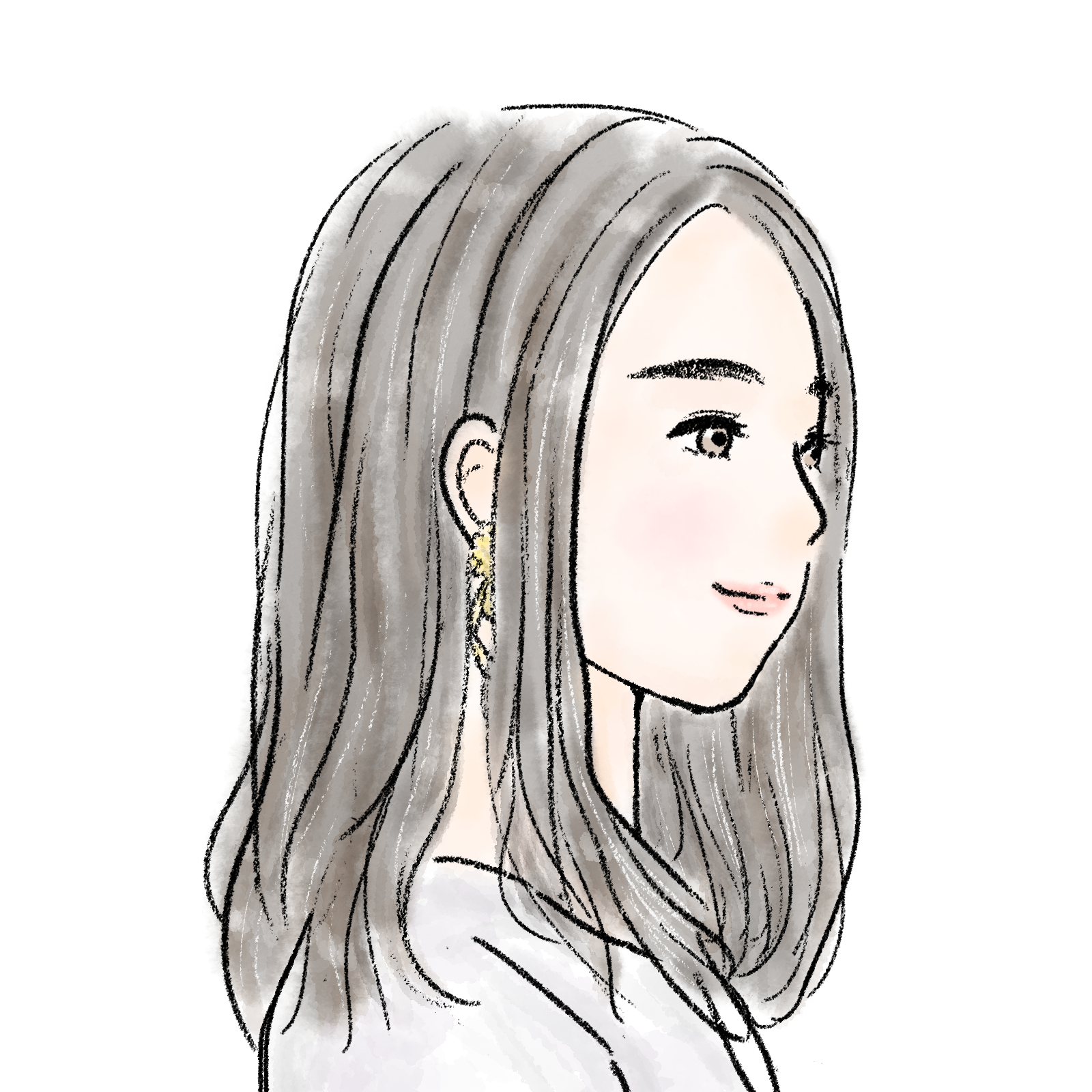
家づくりの打ち合わせで、「巾木や枠の色ってどうすればいいの?」とご相談をいただくことが増えています。
床や壁より注目されにくい部分ですが、空間の印象を左右する意外なポイント。
「標準のままでいいの?」「浮いて見えない?」など、迷いやすいポイントを整理しながら、後悔しない選び方をお伝えします。
1. 巾木・窓枠・建具枠ってどこに使われているの?

巾木(はばき)は「壁と床の境目」、
窓枠や建具枠(ドア枠など)は「開口部のまわり」にある木部です。
あまり意識しないかもしれませんが、部屋の中をぐるっと囲むように配置されており、
“空間の輪郭”をつくるパーツといえます。
また、最近の家では【廻縁(まわりぶち)】と呼ばれる「天井と壁の境目の枠材」をあえて無くすケースも増えています。すっきりとした見た目を優先する場合には、こうした仕上げも選択肢になります。
2. 標準仕様のままでいい?細部の色で空間が変わる
多くの住宅会社では、巾木や枠は白が標準になっていることが多いです。
白は壁になじみやすく、空間を広く見せてくれる効果もありますが、
最近は壁の色をグレーやベージュ、グレージュにする方も増えており、白の枠がかえって目立ってしまうというケースもあります。
「なんとなく標準で…」ではなく、
床や壁の色とのバランスを考えて選ぶことが、満足度の高い仕上がりに繋がります。
壁の仕上がりの色が決まったら、再度確認してみましょう。
小さなパーツと思わず、「全体の中でどう見えるか」がポイントです。
3. 色を選ぶときの3つの視点
① 壁や床との相性で「なじませる」or「際立たせる」
- 【なじませる】→ 壁と同系色で、空間に一体感をもたせ、すっきりした印象に
- 【際立たせる】→ 床や建具に合わせて、空間にメリハリを
巾木や枠は“線”として空間に現れるため、どう目立たせるか(目立たせないか)を意識すると選びやすくなります。
どちらが正解というわけではありません。目指すテイストに応じてバランスを考えることが大切です。
② 統一感を出す?部屋ごとに変える?
基本は全室統一がおすすめですが、和室だけ木目にする、トイレや洗面は壁になじませる色にするなど、
一部だけ変えることで、空間ごとの個性を出すこともできます。ちなみに和室に巾木は付きません。
③ おうちのテイストに合っているか
ナチュラル系ならオーク系の木目、モダン系ならグレーやグレージュなど、
インテリアの方向性に合う色かどうかも大切なポイントです。
4. よくある後悔とその理由
- 床よりも明るい色の巾木を選んで、浮いてしまった
- 壁と同じ白にしたけど、メリハリがなくて物足りない
- 窓枠だけ白くして、他の部分とちぐはぐに見える
→ 小さな部分と思って妥協すると、完成後に違和感が残ることも。
“目立たせたくないのに目立つ”状態が、最も後悔につながりやすいです。
5. コーディネーターからのアドバイス
- 巾木や枠は“線”として空間に現れるため、意外と目に入ります。
- 同じ白でも「真っ白」「黄みがかった白」「グレイッシュな白」などトーンの違いに注意。
- 床や建具と合わせた色選ぶことで、空間にまとまりが出ます。
- 迷ったら、インテリアのイメージ写真を集めて比較してみましょう。
- インテリアの完成度を上げたいなら、細部の色こそ丁寧に選びましょう。
6. まとめ|細部で空間の印象が変わるからこそ、丁寧に選びたい
標準仕様は、あくまで「よく選ばれている平均値」。標準=無難とは限りません。
巾木や枠は、床や壁よりも注目されにくいパーツですが、
完成してから「なんか気になる…」という違和感が出やすい部分でもあります。
最近は「白一択」ではなく、壁や床とバランスを取った色選びが増えてきました。
標準だから、ではなく「自分の家に合うか?」を基準に、写真やサンプルで確認しながら納得の選択をしていきましょう。
インテリアや収納に関するお悩みのご相談やアドバイスは、kuori interior designにぜひお気軽にご相談ください。プロの視点であなたの理想の空間づくりをサポートします。
↓ 詳細はこちらへ

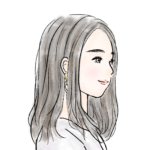
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
これからも家づくりやお部屋づくりのヒントになる情報を発信していきます。
今後もよろしくお願いします。


